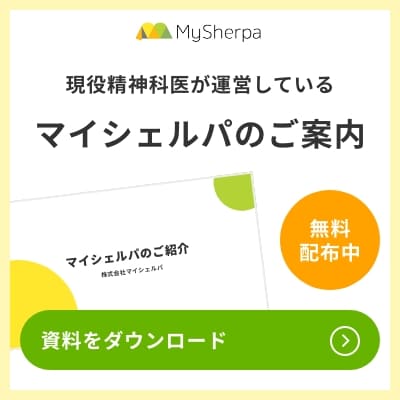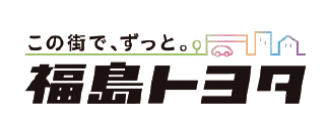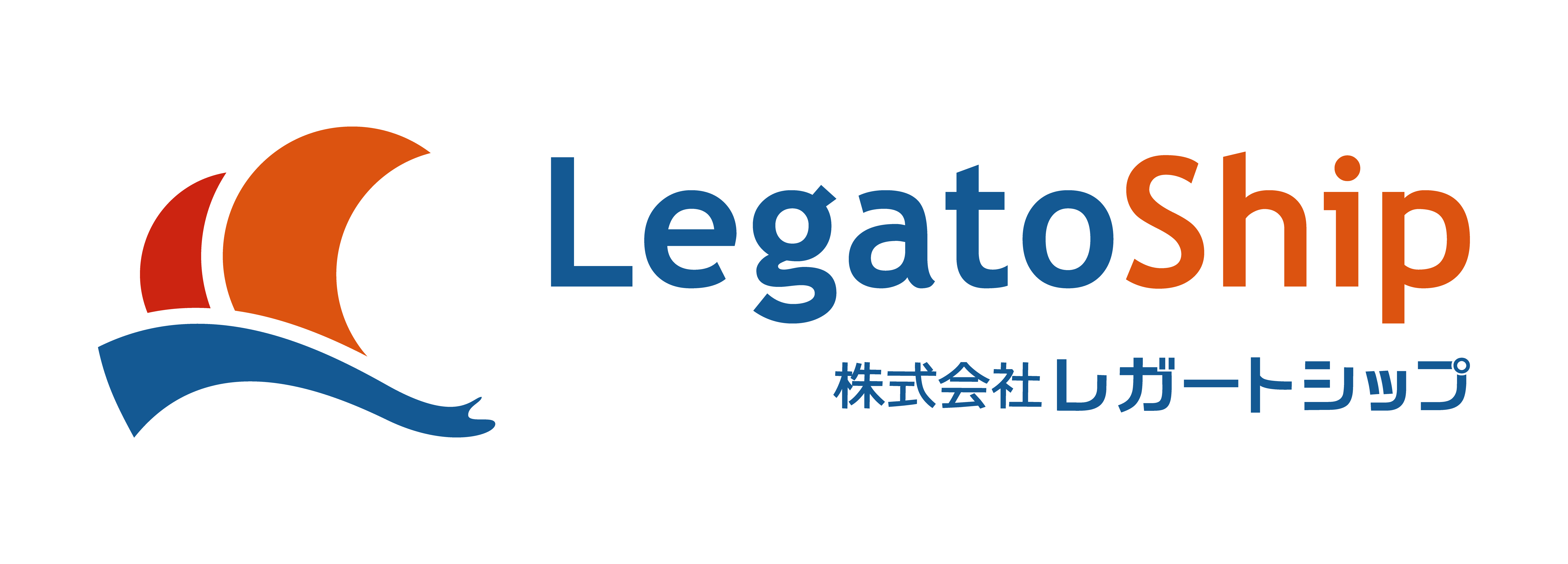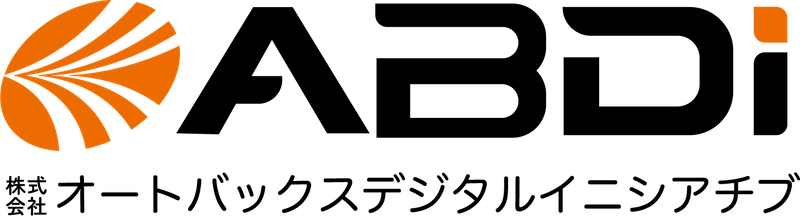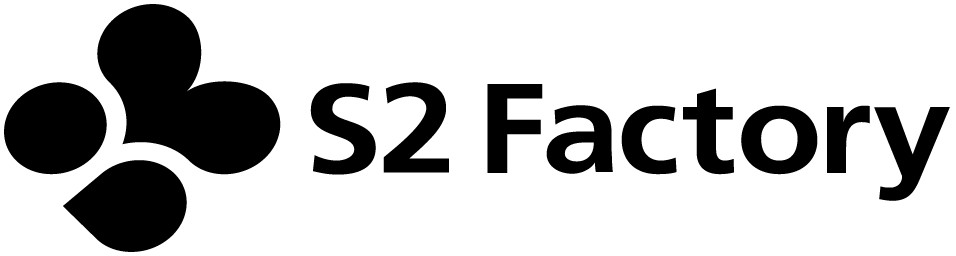法人向けサービス

精神科専門医が提供する法人向け
メンタルヘルス対応の決定版
マイシェルパは、従業員のメンタルヘルス対応のソリューションをワンストップで提供いたします。
メンタルヘルス対応のプロフェッショナルである精神科専門医が運営するサービスですので、安心してお任せください。
導入事例
マイシェルパのご支援内容
- 従業員のメンタルヘルス不調の予防
- 休職者・復職者の対応支援
- 主治医・産業医との連携
- 社内外のハラスメント対応
- 新入社員・中途社員のケア
- 発達障害を抱えた社員への対応
マイシェルパの強み

医学的・科学的に
設計されたサービス体系
医学博士・精神科専門医が運営する信頼のカウンセリングサービスです。医学的・科学的に証明されたサービス設計なので安心して従業員をお任せください。

社内担当者との
密な連携
マイシェルパでは、産業保健に精通したスタッフが担当者様に定期的なフィードバックを行いつつ、企業様ごとのお悩みをどう解消していくかを一緒に考えていきます。

追加料金不要の
定額制
月額¥27,500(税込)〜の完全定額制で、導入費用もゼロ。カウンセリングは全従業員が対象となります。 導入支援や利用促進も無償でお手伝いさせていただきます。

カウンセラーは臨床心理士
・公認心理師のみ
カウンセラーは、厳選された臨床心理士・公認心理師に限定。それにより、必要時に医療機関・産業医とも連携可能。

最短2営業日で
利用開始可能
担当者様は、社内にサイトURLと専用のクーポンコードを配布いただくだけでOK。

提供サービス
メンタルヘルス研修
貴社の従業員や管理職向けに、メンタルヘルス対応の専門家による研修をオンラインで提供いたします。
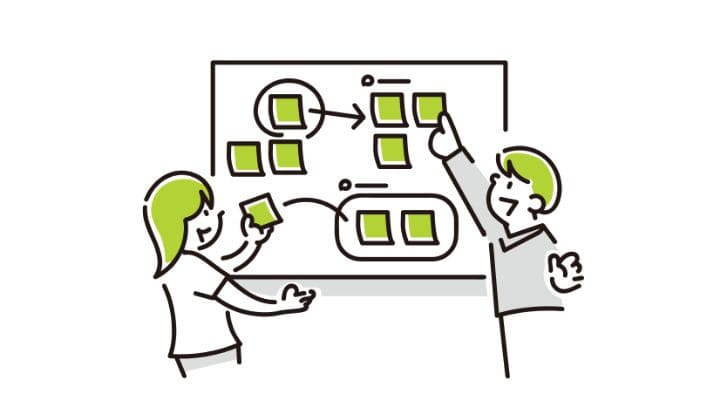

ストレスチェック
メンタルヘルス不調の早期発見のため、法定のストレスチェックをご提供いたします。集団分析も併せて実施いたします。結果に応じてカウンセリングや産業医面談をおすすめします。


オンラインカウンセリング
不調が見られる方には、厳選された専門家カウンセラーによるオンラインカウンセリングを提供いたします。ご利用回数やご利用人数の制限はありません。


スポット産業医(精神科医)
高ストレス者や復職面談など、精神科医産業医による対応が必要な場合は、精神科医がオンラインで面談を行います。
※産業医業務に定める「職場巡視」についてはご対応できかねますので、別の産業医にご依頼いただくようお願いいたします。


導入メリット
メリット.1
従業員のwell-beingの実現
信頼できる相談窓口の設置により、従業員の心理的安全性を高めることができます。
メリット.2
従業員の休職・離職防止
メンタルヘルスの悪化を防ぐことにより、休職・離職者を減らすことができます。
メリット.3
採用コストの抑制
予期せぬ休職・離職によって発生する補充目的の採用コストを抑えることができます。
メリット.4
社内対応コストの抑制
管理部門及び所属部門の、メンタルヘルス不調者への対応工数を抑えます。
マイシェルパのカウンセラーは100%
臨床心理士・公認心理師
精神科医療と連携できるカウンセラーのみを精神科医自身が審査・選定。
さまざまな悩みを持つ方々の気持ちに寄り添い、その悩みをなんとか軽減したいと考える、
強い使命感を持つプロフェッショナルが一丸となり、今までにないカウンセリングを提供していきます。

臨床心理士・公認心理師
臨床心理士・公認心理師。臨床経験6年。
以前はスクールカウンセラーとして学校現場で活動。現在は医療現場で主に認知行動療法、ナラティブセラピーを実施。
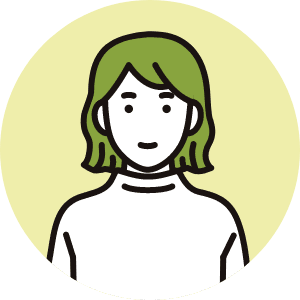
公認心理師
公認心理師・産業カウンセラー・国家資格キャリアコンサルタント。
臨床経験10年。専門は交流分析療法、認知行動療法、コーチング。自治体や企業でカウンセリングやストレスチェック、復職支援を担当。
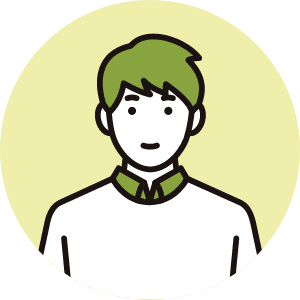
公認心理師
公認心理師・精神保健福祉士・産業カウンセラー。
カウンセラーとして臨床経験13年。前職では7年の人事職を経験し働く人のメンタルヘルス向上に寄与。専門は、認知行動療法、トラウマケア。

臨床心理士・公認心理師
行動心理学とアドラー心理学をベースとしたカウンセリングを実施。区役所の心理相談員として勤務していたことで、発達障害や不登校など、子育てや家族関係に関する相談を多く経験。
料金プラン
提供サービス
メンタルヘルス研修
ストレスチェック
オンラインカウンセリング
スポット産業医(精神科医)
提供サービス
27,500円~/月
※対象人数により変動いたします
詳細料金はお問い合わせください。
詳細はお問い合わせください
ご利用料金
6ヶ月以内に2回以上行う場合は追加料金が発生します。
紙で行う場合は追加料金が発生いたします。
人数制限・回数制限はございません。
「職場巡視」は対応しておりません。
※横にスクロールできます
法人向けマイシェルパの詳細はこちら
法人向けマイシェルパ